安藤証券 コラム
常滑へようこそ(常滑支店より)

|

|

|
2023年7月18日掲載
常滑支店のある常滑はこんな街

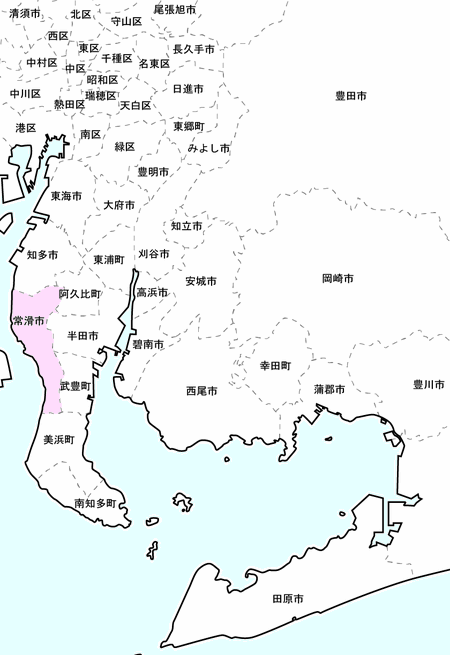
常滑市は名古屋市の南にある知多半島の中央部に位置しています。南北に細長い街で、大部分は丘陵地となっており、平地は海岸沿いの比較的狭い部分に限られています。市街地から伊勢湾に面する場所に中部国際空港(セントレア)があります。
名古屋鉄道の新名古屋駅から常滑駅までは空港行の特急で35分、自動車ならば1時間ほどの距離にあります。
歴史
知多半島中部では、常滑の地名の由来ともなる粘土が豊富に産出されるため陶器が生産されました。六古窯(瀬戸焼・越前焼・信楽焼・丹波立杭焼・備前焼)の一つとして平安時代後期から中世にかけ「古常滑焼」と呼ばれる焼き物が太平洋に沿って全国に広まりました。全国の中世遺跡において出土されたとのことです。
その後、三河国守護である一色氏の被官であった佐治氏(織田信長の姪、徳川幕府2代将軍徳川秀忠の正室である江姫が最初に嫁いだ家)が大野城主(現在の常滑市大野町)となり、常滑は港湾の町として繁栄しました。
その後、徳川家康公の実母(御大の方)の実家である刈谷・水野氏の一族が支配を広げ、佐治氏および水野氏の支配となりました。しかし、両家とも本能寺の変や小牧・長久手の合戦において、敗将方にくみしていたため、支配力を弱める結果となったようです。
また、全国に広がっていた「古常滑焼」は、安土桃山時代に茶の湯が流行し、その嗜好から好まれなくなり他地域の焼き物に押され衰退してしまいました。
江戸時時代中期以降は「廻船」「酒造」「木綿生産」の関連産業が発展し、現在の常滑市街地の原型となったとのことです。

どうして「常滑」って言うの?
「とこなめ」という地名はどうしてついたのでしょうか。
この指名は常滑の土壌に由来するとされています。「常」は「床(とこ)」で地盤。「滑」は「滑らか」という意味で、古くからこの地は粘土層の露出が多くその性質が滑らかなため「とこなめ」と呼ばれ、そうした習俗が地名として定着していったと言われています。
見どころ
常滑名物と言えば「常滑焼」ですが、近年観光スポットとして人気があるのが「やきもの散歩道」です。常滑駅から徒歩10分ほどの場所にある陶磁器会館がスタート地点となっています。散歩道は1.6㎞とお手軽なAコースと、じっくりと4㎞を散策できるBコースに分かれており、散歩道の道順が書かれているリーフレットもあります。
伝統的な窯屋、レンガ作りの煙突を眺めながら常滑焼の体験が出来る工房だけでなく、飲食や買い物もできる店もあり、ぜひ散策してみてください。
また、映画「20世紀少年」のロケ地にもなりました。

今の常滑
2005年に伊勢湾の常滑市沖に中部国際空港(セントレア)が開港されました。それまで静かな焼き物生産の町であった常滑は開港後急速にその姿は変化をしてきています。
人口は一時5万1,000人を割り込むほどに落ち込み、地域産業の停滞、その影響による中小企業の低落が懸念されていましたが、国際空港開港に伴い労働人口が少しずつ増加し、市内中心域を中心に新興住宅地も開発され、2023年5月には人口は5万8,000人にまで増加しています。空港への新アクセスを中心としたインフラ計画も継続されており、近年では大型商業施設の「イオン」や「コストコ」なども出店されました。
平安時代から続く焼き物を中心とした観光産業と人口流入の効果によりこれからも発展が見込まれる町となっており、そんな新旧入り混じる常滑市の常滑駅前に私たちの常滑支店はあります。
「いっぺん(一度)、おいでや(お越しください)、とこなべ(常滑)へ」


